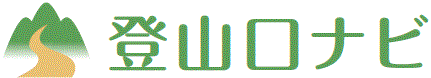大山(表参道~見晴台周回)登山口コースガイド
2026/01/03
三百名山の一つで丹沢の東端に位置し古くからの信仰の山でもある大山(1252m)を、大山ケーブル口から阿夫利神社駅を経て表参道で山頂へ登り、雷ノ峰尾根の見晴台経由で下るポピュラーなコースガイドです。古くから山岳信仰があるため短いながら見所も多いルートです。
【標準コースタイム:登り2時間30分(女坂の場合+5分) / 下り2時間00分(同10分)】

市営駐車場のあるケーブル口から商店や宿坊の並ぶこま参道を進みます。


雲井橋を渡ると大山ケーブルカーの山麓駅があります。大山ケーブルカーは通常9時始発となります。
ケーブル口から15分ほど、駅のすぐ先に男坂と女坂の分岐があります。



<男坂>
男坂は阿夫利神社末社の追分社からすぐに石階段の急登となります。


露岩の平場をはさみ階段が続きます。



八大坊上屋敷跡を過ぎると程なく女坂コースと合流します。


<女坂>
弘法水の脇を通り橋で沢を渡り、地蔵の点在する階段を登ります。
女坂七不思議の子育て地蔵の前で再び橋を渡ります。



七不思議の爪切り地蔵、逆さ菩提樹が連続し、大山寺客殿と前不動堂(龍神堂)の前に出ます。



龍神堂の脇を通り童子像の並ぶ急階段を登ると大山寺です。


大山寺の右脇から登山道方面へ進み、トイレの先で赤い無明橋を渡ります。



潮音洞前を過ぎるとケーブルカーの線路と近接します。
階段の急登が続き、補助の鎖がつけれらた区間を過ぎると男坂と合流します。


大山公衆トイレ脇を過ぎると茶屋処があり、左奥にケーブルカーの阿夫利神社駅があります。
階段を登ると男坂は40分ほど、女坂は45分ほどで下社の拝殿です。





登山道は拝殿の左奥にあり、登拝門をくぐり急な階段から始まります。
表参道コースには登拝門前の一丁目から山頂の二十八丁目まで石柱があり目安になります。



三丁目となる白山神社の碑の脇を通り、石段が続く登山道を進みます。



八丁目には樹齢五~六百年と言われる夫婦杉があります。
杉林の中の急登がしばらく続きます。


十四丁目には牡丹岩と呼ばれる球体の岩が転がります。
石垣のある十五丁目には天狗が鼻を突いて穴を開けたとされる天狗の鼻突き岩があります。



40分ほどで蓑毛からの裏参道と合流する十六丁目です。
展望はありませんがベンチと追分の碑が設置されています。


傾斜は緩みますが、岩が多く転がる尾根道を進みます。
二十丁目の富士見台では二ノ塔尾根越しに富士山を見ることができます。



なだらかな登りとなり二十一丁目の手前でモノレールの線路脇を通過します。
ベンチの設置された二十二丁目を過ぎ、十六丁目から40分ほどでヤビツ峠からのコースと合流する二十五丁目です。



岩の転がる急登区間を進むと御中道の分岐点となる阿夫利神社の鳥居が見えてきます。


さらに階段を登ると二十八丁目の鳥居をくぐり、二十五丁目の分岐から15分ほどで阿夫利神社本社のある大山山頂です。




阿夫利神社本社前からは相模湾の展望が開ける他、東側の広場からは筑波山や房総、都心方面の展望も広がります。





トイレ裏の展望台(御中道)からは丹沢表尾根と富士山を一望することもできます。




見晴台方面の下山路は階段が連続します。
大山の肩を経て20分ほどで唐沢峠・不動尻方面の分岐があります。






さらに階段が続く雷ノ峰尾根を下ります。
西寄りに進路を変えた後、折り返して右側が切れ落ちた狭い区間を通過します。



再び尾根筋を下り、鞍部から僅かに登り返せば分岐から45分ほどで見晴台です。
東屋やベンチが設置され、市街地の展望が開けています。



下社方面の登山道は下り基調のトラバース路で転落防止柵が設置されています。
桟道橋を渡ると右手に御神木の絆の木があります。



さらに下ると二十神社と二十滝が見えてきます。



最後は平坦な道となり大稲荷神社の小さな祠の脇を過ぎると見晴台から30分ほどで下社に戻ります。


(レポート:登山口ナビ 吉田 岳)
◆大山(表参道~見晴台周回)の登山口駐車場情報
大山第二
大山第一
大山臨時
◆近隣の登山口コースガイド
大山(ヤビツ峠~イタツミ尾根)登山口コースガイド
大山(日向~雷ノ峰尾根)登山口コースガイド
大山(浄発願寺奥ノ院~梅ノ木尾根)登山口コースガイド
大山(山ノ神峠~弁天御髪尾根)登山口コースガイド
大山(不動尻~唐沢峠)登山口コースガイド
大山(不動尻~石尊沢左岸尾根)登山口コースガイド
大山(地獄沢橋~大山北尾根)登山口コースガイド
大山(一ノ沢峠~大山北尾根)登山口コースガイド
◆登山口ナビでは、大山(表参道~見晴台周回)のガイドも承っています。
詳細は登山口ガイド受付ページをご覧ください。
<その他の登山口コースガイド>